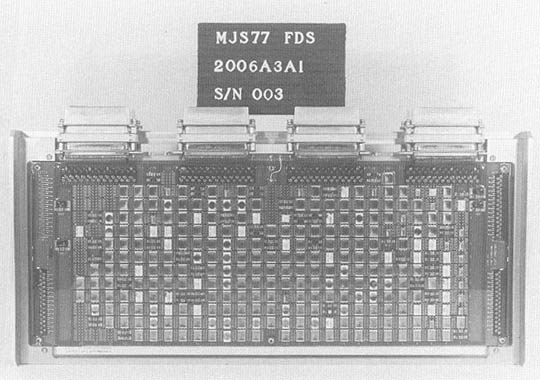初号では、私たちはプロマネ用語なしにプロジェクトを語れないため「プロジェクトって何だろう」という単純な問いにさえ答えられないことに触れた。そして前号では、プロジェクトが人としての在り方と密接な関係があることに触れ、欠かせない側面の1つとして言説的実践を挙げた。複数の人がプロジェクトを「それ」として同一性を持って共有できるのは、発話によって「それ」の見え方・現れ方について表明したり、経験や他者の目を通じて認識を訂正し続けられるからであると。だからこそ、誰の目にも見えない「プロジェクト」という抽象的な存在についても、人は共に知覚して議論し合うことができるのである。
ただ、ここで疑問が湧く。我々は何を「プロジェクト」として認識しているのだろうか。
いや、この問いは誤っているかもしれない。これは認識する前から「プロジェクト」があらかじめ「在る」ことを不当に前提にしてしまっている。繰り返しになるが「プロジェクト」とは誰の目にも見えないのであるー果たして「プロジェクト」はそう呼ばれる以前から存在していたのだろうかーここから、問うべきかもしれない。
社会学者のハロルド・ガーフィンケルは前者を「対応説」、後者を「同一説」と呼んで区別した。対応説では「一方に具体的対象が存在し、他方に対象の概念的再現が存在する」とする一方で、同一説では「知覚された対象と現実の対象は区別されない」と整理したうえで、彼は後者の立場を採用するに至る。極端な話、知覚されることで初めてプロジェクトXが形作られているのであり、Aさんの考えるプロジェクトXと、Bさんの考えるプロジェクトXが別物であるという立場である。「プロジェクトX」の同一性はAさんBさん各々によって仮定されているに過ぎない。
永らく「プロジェクト」の存在を当然視してきたプロマネの歴史からすると、コペルニクス的転回とも呼べる逆転の発想かもしれないが、プロジェクトという概念に対応する具象物がないことを踏まえると、「プロジェクトはそう呼ぶまで存在しない」という発想こそむしろ自然なのではと思えてくる。
この場合「プロジェクトとは何か」という問いに答えがあるかも怪しくなってくるだろう。もし現場ごとに同一性を仮定していくものだとするとプロジェクトの定義などは一般化できないかもしれない。一方で、何かを「プロジェクト」と呼ぶことで組織されている秩序は確かにある。つまり「プロジェクト」そのものよりも「プロジェクトと呼ぶこと」によって可能になることの方が、プロジェクトという現象を理解する上では本質的に重要なのではないか。
プロジェクトは存在している (being) のではなく、成って (becoming) いるという着眼。正確には、私たち自身が成り立たせているのだから達成 (accomplishing) されているという発想。これは先述のガーフィンケルが興した、エスノメソドロジーと呼ばれる社会学的立場に通じている。私たち (エスノ) の実践がどのような方法論 (メソドロジー) に則って「プロジェクト」を達成しているかを明らかにすること。
前号のように人の能力と結び付けてプロジェクトを捉えるときから、すでにプロジェクトは「達成」されているものとして捉えていたとも言えよう。ここでの「達成」はいわゆるプロジェクトの「成功」とは異なる。プロジェクトが成り立ってること自体が奇跡であり、そのことを「達成」と呼んでいるのである。
「何を今さら」と思われるかもしれないが、「達成」できないケースは即「失敗」であることを踏まえると、ここにプロジェクトを上手く進めるヒントが隠れてるとは考えられないだろうか。
プロジェクトは会話のように当たり前のように組織されている。しかし、会話の原理を探究するのにエスノメソドロジーや会話分析の研究を待たねばならなかったように、いまプロジェクトの原理を明らかにする研究が求められていると言えるのではないか。次回はその原理を扱う前提の1つとして、そもそも人はなぜ未来の可能性について語り合えるのか考えてみたい。