この連載を始めてもう6回目になるとは驚きだ。これまで多様な側面からプロジェクトという現象そのものに光を当ててきたつもりだが、不思議と通底するものが見え隠れしているのを感じる。今回はプロジェクト・マネ―ジャーが苦戦しながら対処している「複雑性」とは何なのかを考えてみたい。
デンマークの有名なビジネス・デザインスクールであり、クリエイティブな起業家・PM 人材を輩出する Kaospilot の校長、クリスター・ヴィンダルリッツシリウスも「複雑性」をテーマに博論を執筆しているように、実に探究し甲斐があるテーマだ。複雑性への対処はイノベーションひいては組織経営にも大きな影響を持っていると言えるだろう。
ところで「複雑性」とは何だろうか。ここで、複雑性を分解してみたり (e.g. ステーシー・マトリクス、Management 3.0 の Structure-Behaviro Matrix) 、分類してみたり (e.g. クネビンフレームワーク) することも出来るだろう。しかしながら、複雑性というのは果たして「分解」したり「分類」できるほど外在的なのだろうか。
われわれが普段「複雑」という言葉を使うとき、その基準はかなり主観的であることが多い。辞書にも「物事の事情や関係がこみいっていること。入り組んでいて、簡単に理解・説明できないこと (デジタル大辞泉) 」とある通り、そもそも認識主体であるわれわれの理解・解釈を抜きには語り得ない概念でさえあるのではないか。そしてその解釈によっては、シンプルなものも複雑に、あるいはその逆にもなり得る。つまり、この両極端の性質が同じものに併存しているとさえ考えられるのである。
社会学者のジョン・ローと身体人類学者のアネマリー・モルが共同編集した「Complexities」と題された本によれば、「複雑性」は様々な秩序が同居している「多重性 (multiplicity) 」の結果に過ぎない。だからこそ本書のタイトルは複数形なのだが、例えば、航空機の開発が複雑なのは、空を飛ぶための力学的な秩序だけでなく、乗客の快適性という秩序、パイロットの航空技術を生み出す人材開発の秩序、いかに安価に運用するかという経済的秩序など、挙げれば切りがないほどの様々な秩序の結節点を成しているからである。様々な秩序同士が絡まり合っているさま。こう捉えるならば「複雑性」を単なる形容詞としてではなく、現実に対する解釈あるいは向き合い方として考えた方がしっくり来るのではないだろうか。
プロジェクトの重要な概念の1つに「ステークホルダー」があるが、そもそもなぜ彼らが利害関係 (ステーク) を持っているのかと言えば、彼らの秩序 (スペース) を背負っているからではないか。例えば、校長であり、母親であり、日本人であり、といったアイデンティティとともに、その背景となる秩序 (システム) を引き受けているのである。むしろ根源的には「スペースホルダー」であると表現した方が良いのかもしれない。そして、これは人間のみに該当するわけではない。モノであっても、それが意味づけられて秩序を背負っている限りにおいて「スペースホルダー」であると言えるだろう。
プロジェクト固有の「秩序」があるのだとしたら、こうした様々な併存する秩序 (Multiplicity) を束ねているはずである。David Guile と Clay Spinuzzi はこのさまを「Assemblage」という概念を用いて説明している。プロジェクトが作成物を媒介として推進できるということは、すなわち、そこに関わる様々な秩序のいずれにとっても作成物が許容されているということである。言い換えれば、プロジェクトではモノを創り出すことによって、多くの秩序が共存する新たなスペースを作って、寄り合わせている (Assemble) とも言えるのである。
"That which is complex cannot be pinned down. To pin it down is to lose it."
複雑なものは明確に定義できない。定義することはそれを失うことに等しい。
これは著書「Complexities」の導入章を締め括っている文章である。もしも複雑性が現実の「多重性」の結果であり、むやみに単純化することで失ってしまうのであれば、あるがままに扱っていく実践が必要となってくる。それには多様な秩序を認めつつもその共通となる新たな秩序を生み出していく仕組みが必要だろう。言い換えれば互いの「スペース」に配慮しながら共存できる新たな「スペース」を作っていくことこそが、複雑性 (multiplicity) に対処する方法に他ならないのではないだろうか。次回は、そのスペースこと「場」について考えてみたい。
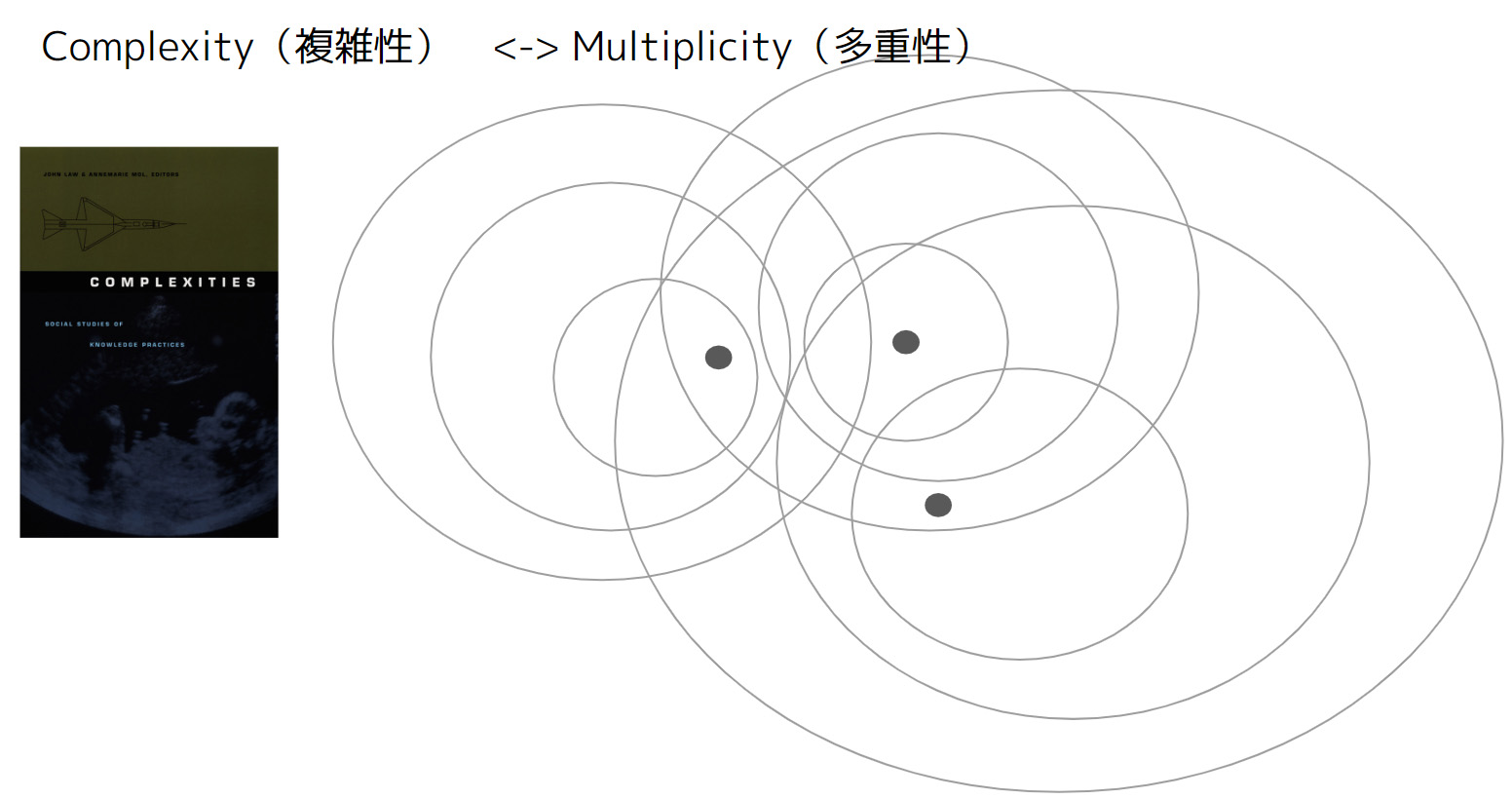

_(14374841786)_-_cropped.jpg)